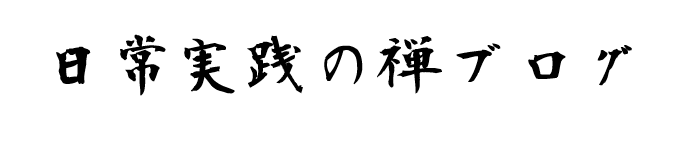彩鳳舞丹霄の意味「鳳凰が美しい空を舞う」
(さいほうたんしょうにまう)
禅問答における皮相だけをみた誤回答

「彩鳳舞丹霄」は色鮮やかな鳥である鳳凰がオスメスつがいで美しい空を舞っているという、めでたい様子を謳った言葉です。
しかし、禅語としての文脈は少し異なる意味合いを帯びてきます。
出典にある禅問答をひも解いて、この言葉の意味を確認していきます。
読み方
「さいほうたんしょうにまう」と読みます。
単語の意味
「彩鳳舞丹霄」は、一般的に使われる禅語ではなく、ほぼ茶掛けでしか使われていない言葉です。
色どり鮮やかでおめでたい印象を与える言葉のため、多用されているのだと思います。
まずは、言葉そのものの意味をみていきます。
彩鳳とは鳳凰(ほうおう)のこと
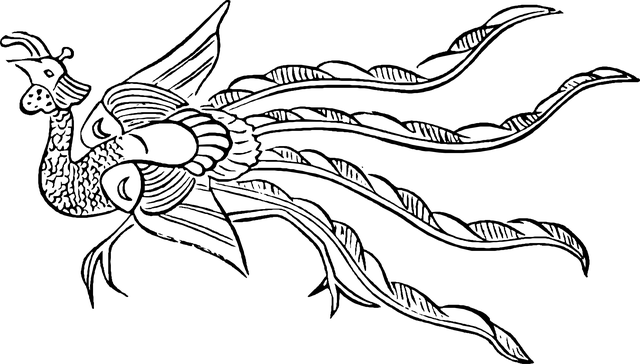
彩鳳は伝説の鳥で鳳凰のことです。実在しませんので、ご注意ください。
鳳凰の特長を挙げておきます。
- 聖人が世に出たときだけ現れる
- 頭は鶏、頷は燕、頸は蛇、背は亀、尾は魚
- 色は黒・白・赤・青・黄の五色で鮮やか
- 霊泉だけを飲み、百年に一度だけ実を結ぶ竹の実のみを食べ、梧桐の木にしか止まらない
- オス・メスのつがいで飛ぶ
なんとも空想的な要素に満ちた存在であることが分かります。
全般にただ空想的ということではなく、縁起のよい要素で固められている点が特徴です。
オスメスのつがいで飛ぶという特徴もあって、この点もめでたい点とされます。
丹霄とは朝焼け・夕焼け

丹霄とは、朝焼け・夕焼けのことを言います。
鳳凰もカラフルですから、言葉として全体に色彩豊かなイメージを描いていることが分かります。
ひとたび羽ばたけば、あらゆる鳥類がこれに従うとされています。
とりあえず、「めでたい言葉」だ

ということで、色鮮やかでめでたい含意がこの言葉にあることが分かりました。
鳳凰自体が聖人が世に出たときのみ飛ぶとされていますから、天下の太平を意味しますし、オスメスつがいで飛ぶというところも夫婦円満・一家安泰といった願掛けになります。
茶掛けに立派な「彩鳳舞丹霄」をお持ちの方はここまで読んでおしまいとしてください。
禅の文脈での意味
めでたい言葉としての「彩鳳舞丹霄」を前節で確認しました。
しかし、少し違和感を覚えます。
禅語で「ただ、おめでたい」とか、「彩り鮮やかで美しい」とか、「幸せを祈念する」といった言葉はないからです。
実際、この言葉の出典に当たれば、禅の文脈でのこの言葉は、めでたい意味を表わす言葉ではないことが明らかです。
むしろ、「めでたい奴」を意味する残念な言葉だったりします。
それでは原典を確認していきましょう。
出典

禅の古書「五燈會元」に掲載されています。
「五燈會元」は、禅の系譜にある特出した禅僧のエピソードをまとめた本です。
「彩鳳舞丹霄」は11世紀の禅僧法演に関する逸話の項に出てきます。
内容

この言葉は有名は「看脚下」が登場する一節に登場する言葉です。
ある禅問答が展開され、その正解が「看脚下」で、不正解が「彩鳳舞丹霄」です。
では、どんな質問があったのでしょうか。
(読み下し文)
三仏、師に侍し一亭上に夜話す。
帰るに及び灯已滅す。
師、暗中に曰く、各人一転語を下せと。
仏鑑曰く、彩鳳、丹霄に舞う。
仏眼曰く、鉄蛇、古路に横たわる。
仏果曰く、脚下を看よ。
師曰く、吾宗を滅する者は、すなわち克勤のみ。
(意味)
法演と弟子3人が山中にお招きを受けた。
よもや帰りが遅くなったが、つい灯りを失ってしまった。
法演は弟子たちに行った。
「この状況を一語で片付けろ」
禅問答の回答
回答1:「彩鳳舞丹霄」
弟子の一人仏鑑は言った。
「鳳凰が夕焼け空を舞っているようだ(めでたいわい)」

暗い夜道を帰らなければなりません。おめでたい言葉で祝っていてもしょうがありません。
直視すべき現実と向き合えておらず、誤答となります。
「彩鳳舞丹霄」は残念ながら、的を射ていないご回答として登場しました。
回答2:「鉄蛇横古路」
二人目の弟子仏眼は言った。
「大きな黒蛇が横たわっている(あぶない、あぶない)」

危機感を認識している点、回答1よりはよいですが、まだまだ修辞的で「どうすべきなのか」、そのものズバリを好む禅としては不正解となります。
回答3:「看脚下」
三人目の弟子仏果は言った。
「足元に気を付けて帰ろう」

法演は言った「仏果、みごとなり」
ただ足元を気を付けるのみ、禅語「看脚下」がここに誕生したました!
解説
暗い山道を明かりなしで下山しなければなりません。
その答えは「看脚下」(足元に気を付けて帰ろう)で正解という逸話です。
この状況で、「鳳凰が夕焼け空を舞っているようだ」ととっぷり暮れた夕焼け空を味わっているようでは、回答としてはおめでた過ぎるので誤答となります。
危機という現実を直視し、足元をみてちゃんと帰るのが正解、まともだというわけです。
禅の文脈での「彩鳳舞丹霄」

したがって、禅の文脈では「彩鳳舞丹霄」は、物事の本質を見据えておらず皮相を捉えた浮ついた軽口ということになります。
実際、「彩鳳舞丹霄」は掛け軸として掲げれば、文字通り、言葉の皮相を捉えて禅の文脈を意に介さない軽薄にしてめでたい人の一丁上がりというわけです。
「看脚下」についてはこちらで解説しています。
茶掛けに遭遇したらどうすべきか

とは言え、「彩鳳舞丹霄」の墨蹟が禅寺でも盛んに作られ、掛け軸として流通している現実もあります。
このような茶掛けに遭遇してどうするべき、社会的な対応策を考えておきましょう。
芳賀幸四郎に倣う
芳賀幸四郎は、大著「五燈会元鈔講和」をまとめた東洋思想学者ですが、茶道者向けの「一行物」では、この禅の文脈をまるまるカットして、最初に述べた「鳳凰が天空を舞うめでたい言葉」として「彩鳳舞丹霄」を解説しています。
これにならって和光同塵、めでたいさまを存分に味わってともに祝うというのが大人と対応
ということかと思います。
正月などのめでたい場面で長寿や多幸を願って使うというのも、これはこれでよしとしましょう。
まとめ
以上、ここまでコントラバーシャルな(議論を呼ぶ)禅語「彩鳳舞丹霄」を見てきました。
触らぬ神に祟りなしだとは思いますが、昨今人気の高い禅語ですので、一応参考までに原典や含意を紹介いたしました。
参考になりましたら幸いです。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。

日常生活のなかにある"禅"文化を探す活動をしています。「心に響く禅語」解説やオンライン座禅会を開催しています。
参考文献:
- 「一行物」(芳賀幸四郎、淡交社)
- 「五燈会元鈔講和」(芳賀幸四郎、淡交社)
画像の一部:
https://pixabay.com/