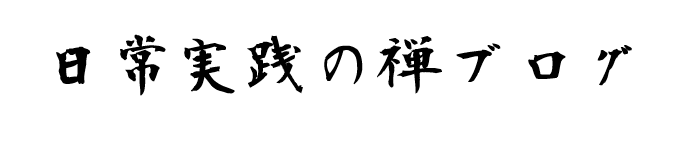「言語道断」の意味:言葉の限界を知って、言葉を断ち切ろう

読み方
ごんごどうだん
意味今日は「ひどいありさまで論外である」という意味で使われることが多いです。
しかし、本来は「仏教・禅の“道”を求めるにあたって、言語は邪魔になる」という意味です。 ...
「活祖」(かっそ)とは:生き仏という意味。一体どこにいるのか。あなたが生き仏になる!?

読み方と意味
「かっそ」と読みます。生きている仏様という意味です。一般には成仏(仏に成る)というと死ぬことを意味しますから、生きている仏というのは矛盾する言葉のように感じます。生きている仏とはどういうことなのでしょうか。
何を伝え ...「この身即ち仏なり」:自分自身が仏であると信じること、これを悟りという

禅の最大テーマの1つが「自信」であるととは、こちらで確認しました。
この自信を持つためのヒントとなる言葉に、「この身即ち仏なり」があります。つまり、自分自身が仏であるという意味です。
実際、仏教というのは、自分 ...
破襴衫裏盛清風(はらんさんりにせいふうをもる)

モノにこだわらず、さわやかに生きる人意味
破襴衫裏(はらんさんり)が分かりづらいので、まずここから解説していきます。
破襴衫裏(はらんさんり)破・襴衫・裏(は・らんさん・り)と分けてることができます。
まずは襴衫(らん ...