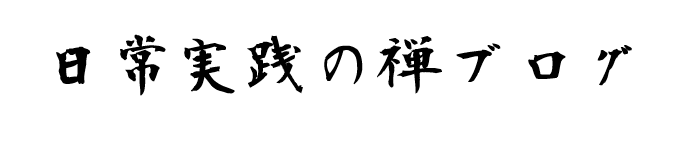動中の工夫は静中に勝ること百千億倍す

禅の中級者以上の方向けの言葉です。
心を落ち着けて日々を過ごすことや、静かに座ることが習慣化した人に対して、同様かそれ以上に大切なことがあると諭してくれる言葉です。 ...
猛虎当路坐(もうこみちにあたりてざす)

非常に難解な文脈で用いられている言葉です。
主に3つの意味合いがあって、禅の文脈の味わいと迫力ある情景が印象的な禅語です。
出典『五灯会元(ごとうえげん)』、『虚堂録(きど ...
真味只是淡(しんみはただこれたん)

禅の考え方を多分に含んだ言葉ですが、出典は禅書ではありません。
まず出典の『菜根譚』の内容から意味を確認し、次に禅の世界観を探索していきます。
出典は『菜根譚』(さいこんたん)洪自誠(1593~1665年)の随 ...
雲外一閑身(うんがいのいちかんしん)の意味

南宋末の禅僧雲外の『雲外雲岫禅師語録』のこちらの一節が元になっているとされています。
三十余年無故人
只留雲外伴閑身
書き下し文三十余年故人なし
ただ雲外に留まりて閑身を伴う
泥仏不渡水 神光照天地の意味「大切なのはモノではない」
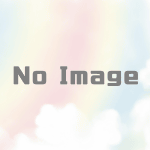
「泥仏不渡水 神光照天地」はそれぞれ単独に使われることの方が多い禅語です。
泥仏不渡水は「金仏不渡炉」 「木仏不渡火」と合わせて趙州の三転語として知られている偶像崇拝を否定 ...
大道無門の意味「悟りの道にはどこからでも入れる」

大道無門(だいどうむもん)は、「禅の悟りの境地を意味する大道には特に入口がなく、だれでもいつでもどこでも入れるよ」という意味です。
禅問答をまとめた禅書「無関門」の序文を飾る非常に重要な言葉です。 ...
「別是一家風」(べつにこれいっかふう)の意味:私もOK、あなたもOK。それぞれ自分らしくという禅語

べつにこれ、いっかふう
意味
それぞれのやり方があるということ。
禅宗にも宗派がいくつもありますし、茶道・華道にも家元がいて、それぞれやり方は違います。 ...
「雲静日月正」の意味

禅語「雲静日月正」(くもしずかにして にちげつただし)は、特別なことは何もない穏やかな日を味わう言葉です。
日・月となっていますので、昼間のイ ...
「着衣喫飯」(じゃくえ きっぱん)の意味:ほとんどの人の幸せを確定させる魔法の言葉

じゃくえきっぱん、と読みます。
意味は服を着ること、ごはんを食べること。
意味・当たり前を当たり前に行うこと、
・自分のことは自分でやること、
・最低限のことをしっかりやるこ ...
「担板漢」(たんばんかん)の意味:人はだれしも視野を狭める板を担いで生きている

「たんばんかん」と読みます。板をかつぐ男という意味です。読み方としても「板をかつぐ男」でもよいかと思います。
意味大きな板を右肩に乗せて担ぐと右側の視界が遮られます。左肩に乗せれば、左側の視界が遮られます。もの ...
「活祖」(かっそ)とは:生き仏という意味。一体どこにいるのか。あなたが生き仏になる!?

「かっそ」と読みます。生きている仏様という意味です。一般には成仏(仏に成る)というと死ぬことを意味しますから、生きている仏というのは矛盾する言葉のように感じます。生きている仏とはどういうことなのでしょうか。
何を伝え ...一滴潤乾坤の意味:ひとしずくが天地に雨の恵みをもたらす

一滴潤乾坤は、「いってきけんこんをうるおす」と読みます。
乾坤は天地を意味しますから、一滴の水が大地を潤すというようなイメージになります。
荒唐無 ...
「清光無何処」(せいこういずれのところにかなからん)の意味:清き光はどこにあるのか、至るところにあるではないか。刮目せよという禅語

清光無何処は「せいこういずれのところにかなからん」と読みます。虛堂録には上の句があって、「此夜一輪満、清光何處無です。上の句は「このよいちりんみちて」です。
続けて訓読みすると、「この夜一輪満ちて、清光いずれの所 ...
「この身即ち仏なり」:自分自身が仏であると信じること、これを悟りという

禅の最大テーマの1つが「自信」であるととは、こちらで確認しました。
この自信を持つためのヒントとなる言葉に、「この身即ち仏なり」があります。つまり、自分自身が仏であるという意味です。
実際、仏教というのは、自分 ...
「随所に主となる」の意味:どこにいても主体的であれ

随所作主(ずいしょさくじゅ)
禅語「随所に主となる」を取り上げます。
臨済宗の宗祖である臨済の言葉ですが、ストレートな禅の気風を味わうことのできる一言です。
それでは解説していき ...
忘筌(ぼうせん)の意味:「釣り竿を忘れました」の真意とは

「忘筌」(ぼうせん)とは荘子外物篇に出てくる言葉です。
筌は魚を取る道具のことで、魚を取ったら釣り竿のことは忘れてしまうという文脈で出てきます。
現代的な解釈では、目的こそが重要で手段のことなど忘れてしまえ、と ...
両忘(りょうぼう)の意味「物事を比べて考えるな!」

禅の世界では多用される禅語のなかでも有名な一言です。例えば、明治時代の山岡鉄舟らが結成した参禅会は、両忘会と名付けられています。
よく用いられる言葉ではあるものの ...
無礙(むげ)の意味:さまたげるものがない状態を示す禅語。自分自身を不自由にしているものとは何か

難解な禅語、「無礙」(むげ)を考えてみたいと思います。そっけなく扱うことの意味で「ムゲにする」といいますが、この場合の漢字は「無下」でまったく意味が異なります。「礙」が見慣れない漢字なだけに、直感的に理解しづらいところが無礙の難解さの ...
「知足」(ちそく)の意味::満たされていることを知ること。満たされない人を餓鬼という

知足は、「ちそく」と読みますが、「足るを知る」と呼んでもよいかと思います。意味合いとしては、「ほどほどで満足せよ」という解釈が一般的です。つまり、「多くのものは100点満点とはいかないから、ほどほどのところで十分だと思うことが幸せにな ...
達磨の禅語「不識」(ふしき)の意味:「知らねーよ」。思い切って開き直ってしまおう!使い方と例文付き

不識は「ふしき」と読みます。“知らない”という意味ですが、ニュアンスとしては「しらねーよ」「興味ないよ」といった意味になります。
何について関心がないのかが重要になりますが、その鍵はこの言葉を発した達磨(ダルマ)のエピソー ...