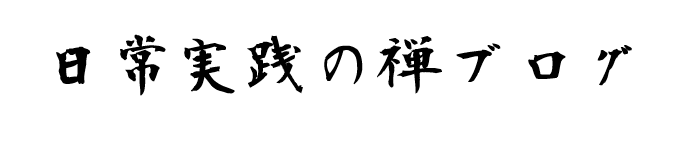頓悟・漸悟(とんご・ぜんご)の意味:悟りは発展段階するのか、あるいはON/OFFのようなものか

とんご・ぜんご
悟りとは、いかに得れるものか。よく知らない。頓悟は突然に、いきなり、一気に。漸悟は少しずつ、だんだんと、順を追って。
後者はぴんとこない。そのような段階を誰が描いたというのだろうか。悟りとは成長 ...
鐘楼上念讃(しょうろうのうえにねんさんす)の意味を考える

薬山は野菜くずと麦くずを煮て空腹を満たし、牛小屋で修行した。大伽藍で大いに成就するなら、大大伽藍でも建てればよかろう、てなものである。大燈国師は20年の乞食生活、橋の下で暮らしたとの話である。鐘楼上念讃 牀脚下種菜ともいう。仏殿がなけ ...
夢

人生畢竟夢なり。とあれば、自暴自棄に刹那を生きるのか。そうではない。その瞬間瞬間を三昧の境地で、専心務めよと。以前見た森美術館のオノ・ヨーコの夢がよかった。ジョン・レノンの夢ともいうべきか。しかし、ジョンやヨーコの夢と、禅の夢はだいぶ ...
禅語「黙雷」(もくらい)の意味:雷のように恐ろしい沈黙がある。沈黙ほど多弁なものはない。

今北洪川の黙雷という軸を拝見した。ネットで調べた限りだが、洪川には武田黙雷という弟子がいたようである。建仁寺の管長を務めている。しかし、黙雷はもう少し調べてみると、淵黙雷声(へんもくらいせい)とあってそこから来ているのだろうか。釈迦が ...
大憤志(だいふんし)

志を持って、決して退かないこと。これなくして、ことは得られないと。ことを得るまで続ければよい。志といってしまうと精神論のような話になってしまいがちである。意思が強い、弱いとか。そうではなくてあくまで結果論なのではないだろう。得られるま ...
禅語「如是」(にょぜ)の意味:かくのごとし、このとおり。そのまま、ありのままに。

かくのごとし、このとおりとなるが、如是法と同義で考えるべきだという。すべての根本の在り方を如是法である。如是、如是でそのまま、そのままと、Let it be, let it beというようにも捉えることができるようだ。そのものをそのま ...
雪竹(せっちく)の意味:雪に負けずに緑を讃える竹に、逆境に負けない強さを見出す言葉

冬空から雪がしんしんと降ってきて、竹は静かにその雪を受け止めている。雪は竹のそばにあって、ますます白く、竹は雪のそばにあってますます青い。竹は一年中その色を変えないので、不老不死のめでたいものの象徴として、松とともに禅語によく登場する ...
施無畏(せむい)

畏れ(おそれ)が無くなることを施す。すなわち、恐れなくていいようにしてあげること。観世音菩薩のことを施無畏者と称する。誰しもに不安がある。怖いという気持ちがある。それは何に対する恐れなのか、それは人それぞれである。上司や先輩が怖いとい ...
無着(むじゃく)

着は執着、すなわち執着するなと。勿嫌底法(嫌う底の法なし)である。茶道にあっては、”お好み”の世界である。道具への”こだわり”、一味違うといったことに面白さを感じる文化という側